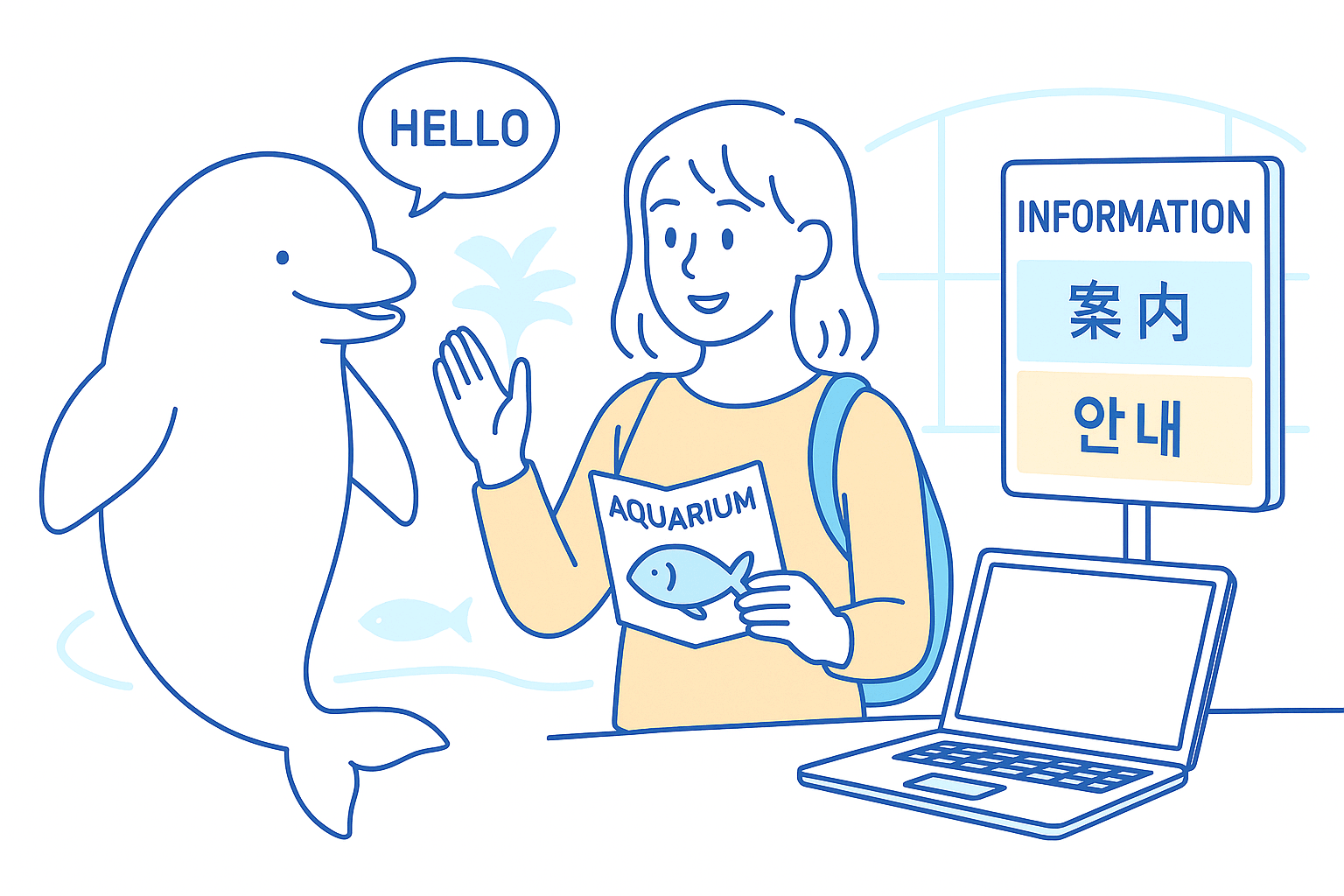
訪日観光客の定番スポットである水族館では、多言語対応の質がそのまま来館者満足度に直結します。しかし、「どの言語を翻訳すべきか?」「どの程度まで対応すればよいか?」と悩む広報・運営・企画担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、水族館における翻訳言語の選び方と、効果的な対応の優先順位について、実例を交えてわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 水族館に多い外国人来館者と対応すべき翻訳言語
- 来館目的や施設立地に応じた翻訳内容の優先順位
- 多言語対応を進める際の実務ステップと注意点
- よくある失敗例とその対策
- 都市型・観光地型など施設タイプ別の言語セット提案
なぜ水族館でも「翻訳言語の選定」が重要なのか?
水族館は展示解説・安全案内・利用ルールなど、多くの情報を正確に伝える必要がある施設です。そのため「何語に」「どの情報を」翻訳するかの選定が非常に重要です。
翻訳対応を感覚的に進めると、実際には使われていない言語にコストをかけてしまったり、重要な案内が翻訳漏れしてしまったりといった事態が起こりやすくなります。水族館においても「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確にし、翻訳対象の優先順位を整理することが、無駄なく効果的な対応につながります。
水族館に多い外国人来館者と国別特徴
2025年上半期の統計によると、訪日外国人の中でも水族館を訪れる傾向が強いのは、以下の国・地域です:
- 韓国
- 中国(本土)
- 台湾
- アメリカ
- 香港
- タイ
- フィリピン
特に東アジア圏(韓国・中国・台湾・香港)からの団体旅行・家族旅行が多く、館内移動や注意事項、施設ルールの案内を多言語で提示するニーズが高い傾向にあります。
一方、英語圏の個人旅行者は、展示物の背景や生物の情報など、やや詳しい解説に興味を持つ傾向があります。
翻訳対応すべき言語の優先順位とは?
まずは以下の4言語を基本セットとして検討するのが現実的です:
- 英語:国際標準であり、英語圏以外の訪日客も一定程度理解できる
- 中国語(簡体字):中国本土向け。団体旅行客が多い
- 中国語(繁体字):台湾・香港向け。安定した来館が見込める
- 韓国語:短期旅行や家族連れが多く、館内案内の翻訳ニーズが高い
加えて、地域特性や来館者データに応じて以下を検討:
- タイ語・ベトナム語:東南アジアからの団体旅行が多い地域向け
- フランス語・スペイン語:欧米圏の個人旅行者が多い都市型施設向け
言語数を増やしすぎず、「英・中(簡・繁)・韓」を基本に、実情に合わせて段階的に対応するのが理想です。
翻訳言語の選定を間違えるとどうなる?(失敗例から学ぶ)
ある沿岸部の水族館では、地元自治体との連携からタイ語対応を導入しましたが、実際の来館者にはほとんど需要がなく、印刷物の更新コストだけがかさむ結果に。一方、別の都市型施設では、韓国語対応を後回しにしたことで、団体客から「案内がわかりづらい」と苦情が出て対応に追われた事例も。
こうした例からも、「なんとなく対応」ではなく、データに基づいた翻訳言語選定の重要性がよくわかります。
水族館タイプ別:おすすめ翻訳言語セット
都市型(交通アクセス良好・個人観光客中心)
→英語、中国語(簡・繁)、韓国語+フランス語またはスペイン語
観光地型(団体・家族連れ中心)
→英語、簡体字、繁体字、韓国語
地方の小規模水族館
→英語+1〜2言語(自施設の来館傾向に応じて)
来館者の属性や施設の立地に応じた選定が、無理なく続けられる多言語対応につながります。
よくある質問(Q&A)
Q:英語だけでも十分ですか?
A:最低限の案内は可能ですが、非英語圏(中国・韓国など)では通じにくく、母語での案内があることで満足度が格段に上がります。
Q:AI翻訳で対応しても大丈夫?
A:簡易案内には有効ですが、展示解説や注意事項などは人による翻訳+チェック体制を推奨します。
まとめ
水族館の多言語対応は、「翻訳の数」よりも「伝わる質」が問われます。まずは自施設の来館傾向を確認し、必要な言語と翻訳内容に優先順位をつけることから始めましょう。
英語を基本に、中国語や韓国語などの主要言語を丁寧に対応することが、外国人来場者の満足度向上とリピーター獲得につながります。



